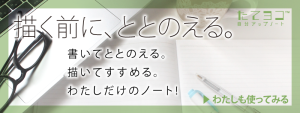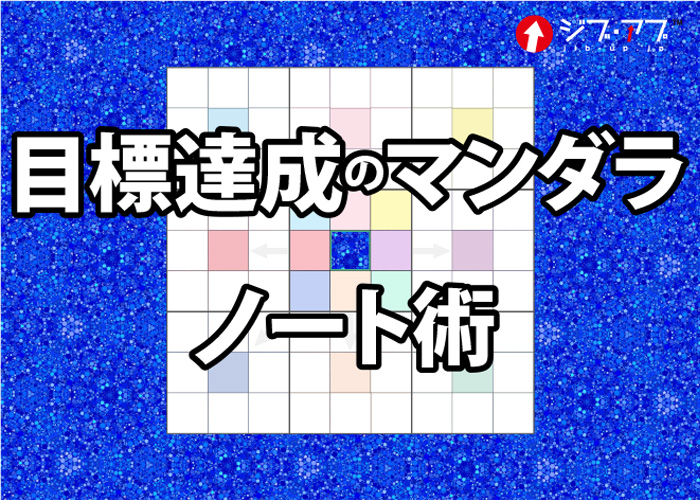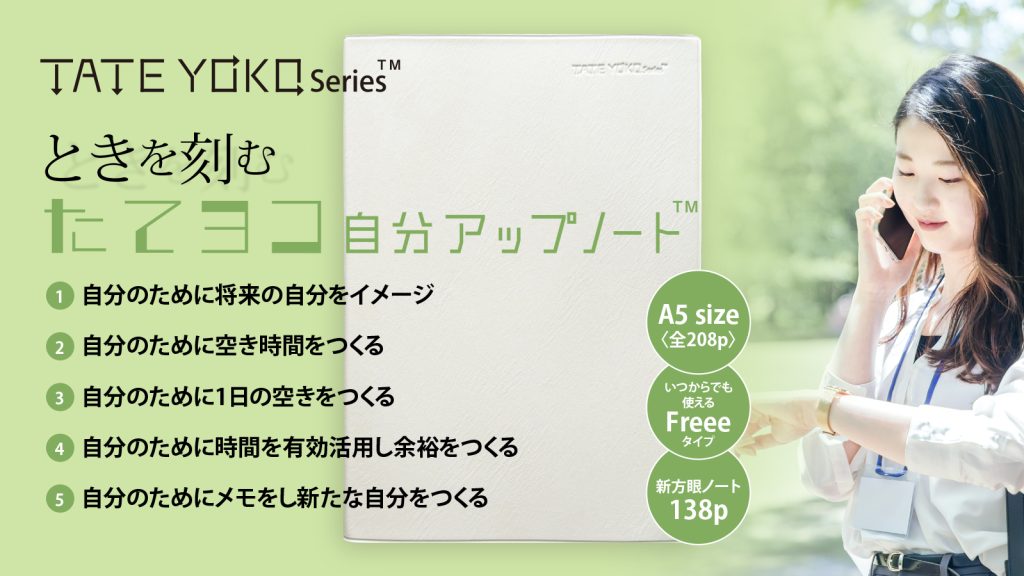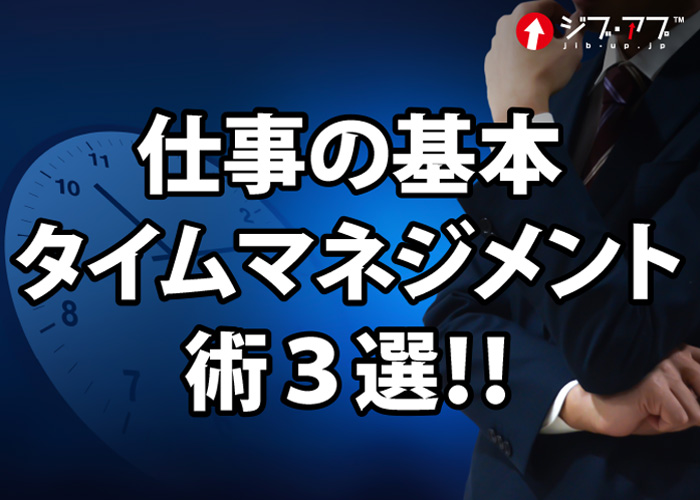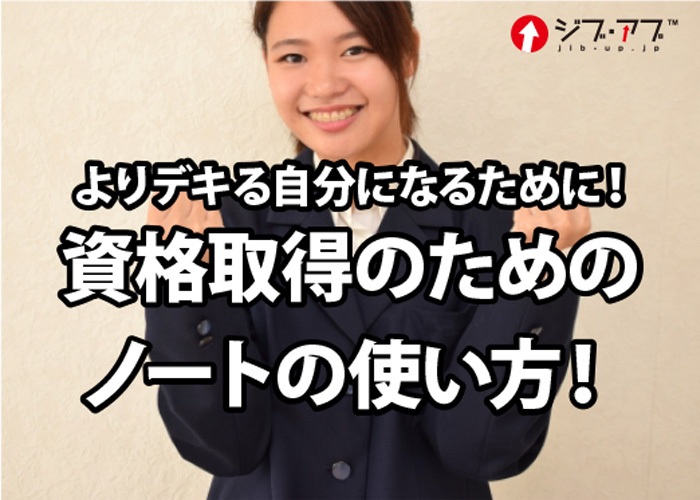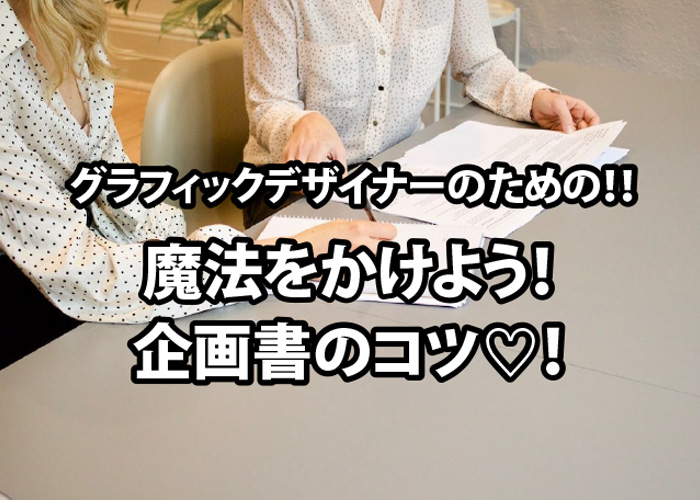
新人デザイナーさんへ。
心に届く企画書は、センスだけでなく“段取り”から生まれます。
ここでは、ニーズ理解→独自性→ビジュアル→ストーリー→見せ方→費用と進行→FB→プロ意識まで、
クライアントに刺さる提案の流れをやさしくまとめました。
▶“アートディレクター”が考えたノートとを使うと“どうなる!?”
1. ニーズをつかむ:ヒアリングの“型”を持つ
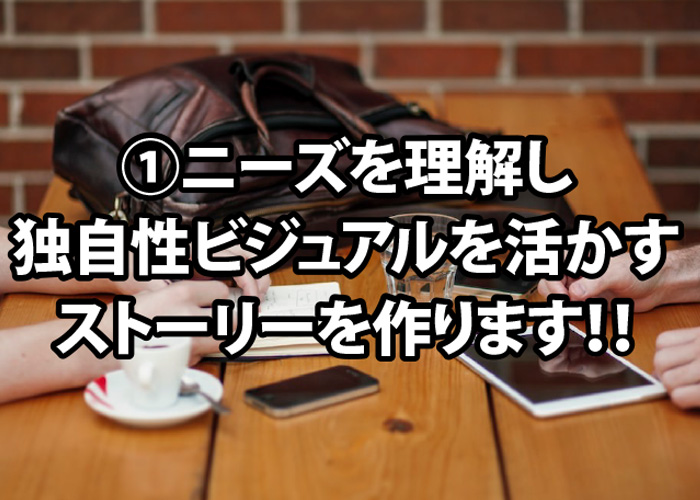
相手の言葉で課題を言い直せたら半分勝ち。
目的:何を達成したい?(KPI/行動変容)
ターゲット:誰に・どのシーンで・何を感じて欲しい?
制約:納期/予算/使える素材/法務チェック
好みとNG:参考例3つ/ブランドの守るべき一線
👉 ヒアリングは録音+要点を即メモ。相手の表現をそのまま見出しに使うと、のちの合意形成が早いです。
2. 独自性を立てる:あなた“ならでは”の提案軸
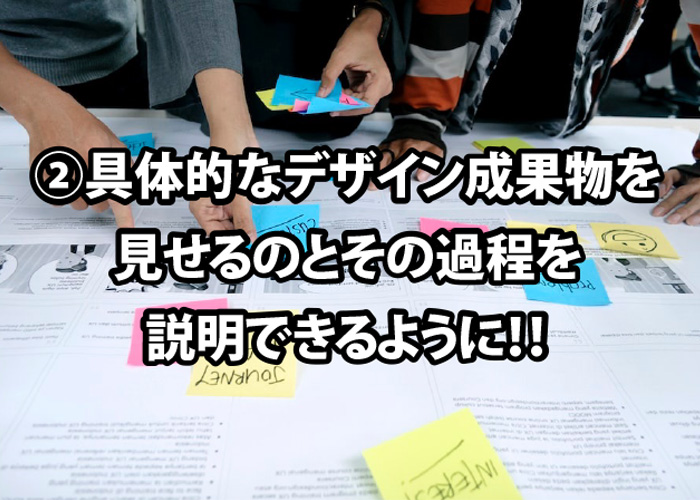
「他社でも言える」案は埋もれます。
1行コンセプト(例:“○○の『らしさ』を、余白と質感で語る”)
差別化の根拠:ターゲットの未充足/競合の欠落点
期待効果:見た瞬間の印象+行動の変化
👉 コンセプトは短く・感情+機能の両輪で。
👉 思考もスケジュールも書ける『たてヨコ自分アップノート』を見る➚
3. ビジュアルで語る:色・書体・レイアウトの理由
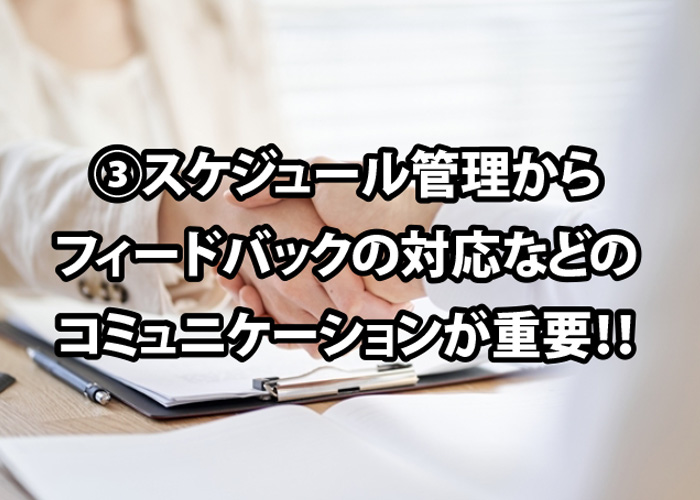
色:役割(ベース/アクセント/ニュートラル)と理由(心理・文脈)
書体:見出し/本文/数字の役割分担と可読性
レイアウト:視線誘導→CTA(問い合わせ・購入など)
👉 すべてに**「なぜ?」の一言を添える。好みではなく目的**で説明。
4. 物語にする:ストーリーテリングで腹落ち
Before(現状のモヤモヤ)→コンセプト(約束)→After(体験の変化)
ユーザーストーリー:“Aさんはこの場面で○○を見て、△△したくなる”
👉 **“誰が・どこで・どう感じるか”**が入ると強い。
5. 見せ方の鉄則:成果物+プロセスで安心感を
モックアップ(手早いラフ→原寸検証)
比較案(主案/堅実案/攻め案)※差は意図で説明
再現情報:色コード/フォント名/画像権利
👉 「こう作るから、こう仕上がる」を工程で見せると納得度UP。
6. 透明性:スケジュールと費用を“見える化”
里程標:ヒアリング→一次案→修正→最終→入稿(検収)
作業内訳と費用:何に何時間かかるかの概算
変更管理:範囲変更時の見積更新ルール
👉 先にルールを出すほど信頼されます。
7. フィードバック設計:揉む前提で勝ち筋を作る
FB窓口・回数・期限を明記(例:2回/各2営業日内)
依頼テンプレ:「良い点/気になる点/目的に照らした要望」
議事メモ:決定/保留/宿題を日付でログ化
👉 感情の交通整理=合意形成コストを下げます。
8. プロフェッショナリズム:振る舞いがブランド
期限厳守・既読スルーしない・確認はYes/No+期日
変更は早報・中報・終報で。推奨案も添える
細部:余白・禁則・画像権利・色校の段取り
👉 “丁寧さ”が次の指名に直結。
👉 新発想!スケジュールも思考も書ける『たてヨコ自分アップノート』を見る➚
企画書テンプレ
表紙:案件名/日付/貴社名・当方
1. 背景・課題(ヒアリング要約)
2. 目的・KPI(行動・指標)
3. ターゲット(人物像・シーン)
4. コンセプト(1行)+狙い
5. クリエイティブ方針(色・書体・トーン&マナーの理由)
6. 提案案(主案/代替案/モック)
7. 期待効果(Before/After・導線)
8. 進行計画(マイルストーン表)
9. 見積・条件(内訳/権利・再利用)
10. FBフロー(回数・期限・窓口)
付録:再現情報(色コード・フォント名・使用素材権利)
よくある質問(FAQ)
Q1. 企画書は何ページがベスト?
A. 目安10~15P。長い場合は最初に1枚の要約シートを。
Q2. モックはどこまで作る?
A. 3秒で意図が伝わるレベルまで。印刷物は原寸で雰囲気確認。
Q3. 予算が固まっていない時は?
A. Good/Better/Bestの3段階で、範囲と期待値をセット提示。
Q4. 好みで押し戻されたら?
A. 「目的に照らすと、A案は○○が強みです」と基準で会話。
Q5. 修正の線引きは?
A. 事前に回数・範囲・追加条件を書面化。揉めない仕組みが先。
まとめ
刺さる企画書=ニーズ理解 × 独自性 × 説明責任
物語・見せ方・進行と費用で“安心”を、FB設計で“前進”を。
プロ意識の積み重ねが、次の指名につながります。