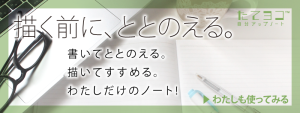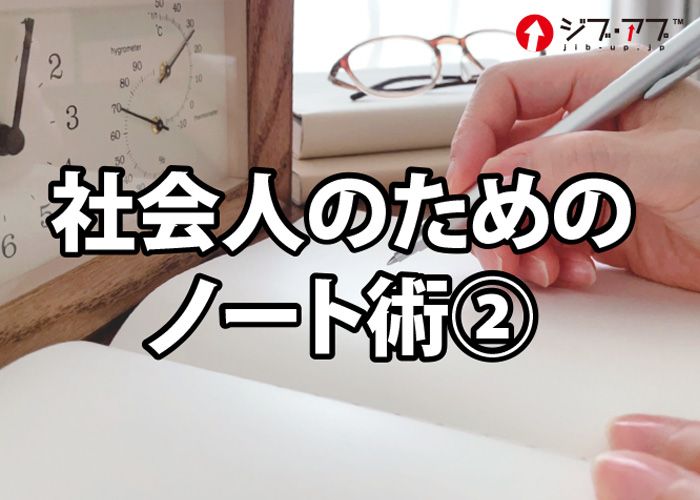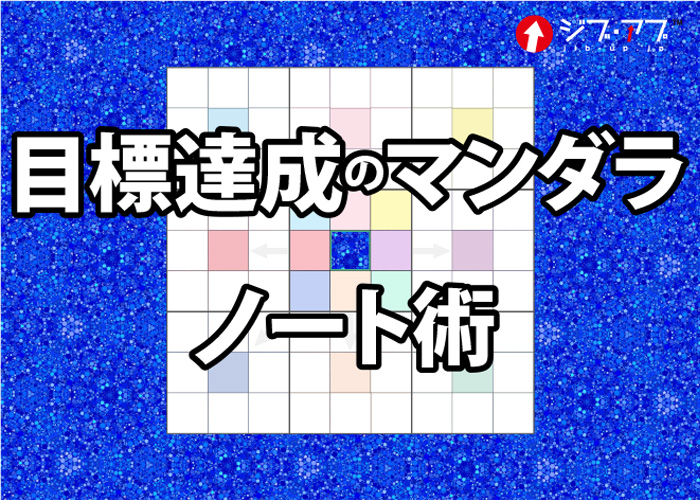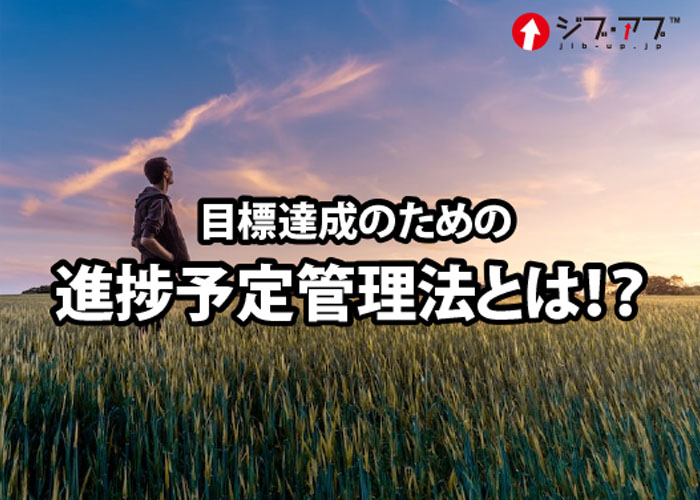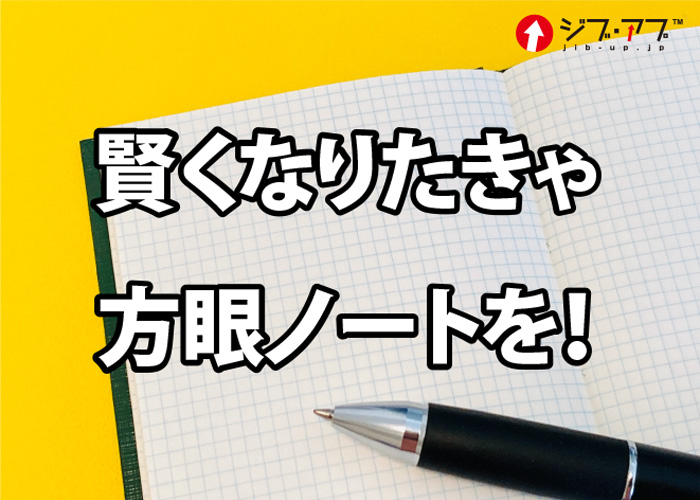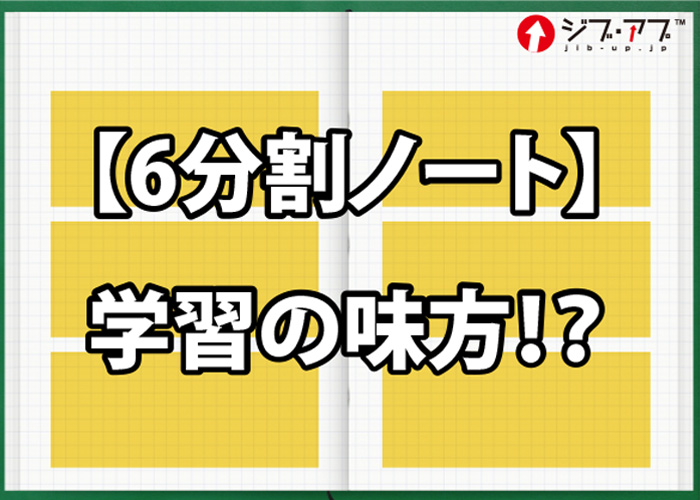いいデザインは**“思いつき”ではなく“プロセス”**から生まれます。
本記事では、アートで終わらせず、クライアント(=エンドユーザー)価値に着地させるための7ステップを、やさしく実践目線でまとめました。
ポイント:
日常から“拾う” → 量を出す → 形にして“見せる” → 客観視で磨く
コンセプト/ターゲットを外さない(=趣味化させない)
▶“アートディレクター”が考えたノートとを使うと“どうなる!?”
① 日常で“拾う”:インスピレーションを貯金する習慣
観察ノート/写真ログ:花の配色、看板の字間、夕景のグラデ…短いキャプション付きで保存
定期インプット:展示会・書店の装丁・街歩き・旅。出典と日付をメモ(後で参照できるように)
小さな喜びを言語化:「なぜ良い?」を一言で。*“影の青味が気持ちいい”*など
コツ:毎日3つ“良い発見”を書く。量が感性を育てます。
② みんなで出す:ブレインストーミングの土台づくり
ルール:批判しない/質より量/他者案に“乗せる”
場づくり:タイマー10分×3セット、ポストイット1枚=1アイデア
可視化:壁に貼って**目的(誰に、何を、どう)**に近い順にグルーピング
進行役の口ぐせ:「いいね、じゃあどう見せる?」—解像度を1段上げる合図。
③ “数”を重視:まずは100個
数=発想の筋トレ。キレイさは後回し
同義語・対義語、サイズ・素材・時間帯など軸を変えて増やす
10個で止まったらお題をズラす(ターゲット年齢・季節・価格帯)
目安:個人30、2人で60、3人で100。数が組み合わせを生む。
👉 思考もスケジュールも書ける『たてヨコ自分アップノート』を見る
④ モックアップで“視える化”:原寸で検証する
まずラフ(手で速く)→デジタル(版面、余白、階層)
媒体前提で確認:印刷物は原寸出力/スマホは実機表示
テスト観察:3秒テスト(伝わる?)/3mテスト(遠目の強さ)
完璧不要。**“早く雑に作って、早く直す”**が正解です。
⑤ 色とフォント:印象の8割を決める“設計”
色
役割を決める:ベース/アクセント/ニュートラルの3層
心理とコントラスト:明度差をWCAG目安で確保(可読性)
文化文脈:ターゲットの生活圏で不協和にならないか
フォント
目的に合わせたペアリング(見出し/本文/数字)
文字組の基礎:字間・行間・約物処理(ここで“プロ感”が出ます)
迷ったらまず“読みやすさ”。装飾は理由がある時だけ。
メモ:ブランド案件は色コード/書体名/字送りをノートに固定(再現性=信頼)。
👉 新発想!スケジュールも思考も書ける『たてヨコ自分アップノート』を見る
⑥ あえて“手を止める”:休憩が発想を救う
25分集中+5分休憩(軽い散歩・伸び)
昼寝10–15分/白紙を眺める“ぼんやり時間”
詰まったら問題を書き言葉に:「誰に」「何を」「どう感じさせたい?」
アイデアは追いかけるより、迎える準備。休むのも仕事の一部です。
⑦ フィードバック:他者視点で“価値”に着地
聞き方:「一言でどう見える?」「対象は誰に見えた?」(好みを超えて機能で聞く)
受け止め方:感情と事実を分け、修正メモを3本に絞る(効果が大きい順)
ログ化:決定/保留/宿題 を日付つきでノート管理
目的は“勝ち負け”ではなく成果を強くすること。感謝と検証をセットで。
便利テンプレ
アイデアシート(1案=1枚)
フィードバック記録
まとめ:アートにしない。“目的に届く”発想プロセスを
日常で拾う → 量産 → 見える化 → 設計(色・字) → 休憩 → FB → 改善
ターゲット/目的/媒体文脈を外さない限り、発想は何度でも深められます。
明日からは、まず**「100案メモ」→「原寸モック」→「3秒テスト」**でどうぞ。